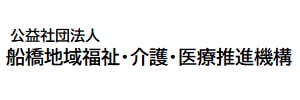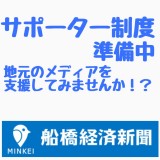船橋大神宮のふすま絵、82年ぶりに新調 船橋在住・綿引はるなさんが描く

船橋大神宮として知られる意富比神社(船橋市宮本5)の社務所のふすまが82年ぶりに新調され、3月25日、報道関係者向けに公開された。
ふすま絵を手がけたのは、船橋市在住の日本画家・綿引はるなさん。芝山中学校出身の綿引さんは東京芸術大学日本画専攻を卒業後、大学院を経て日本画家として独立。伝統的な技法を駆使し、花や鳥など身近な自然をモチーフに作品を制作している。安宅賞や万葉日本画大賞受賞など多数受賞し、東武百貨店船橋店で何度も個展を開いている。
今回のふすま絵の制作は、社務所の大規模改修工事の一環として行われた。同神社の宮司・千葉敏さんは「新しいふすま絵は、船橋にゆかりのある人物に手がけてもらいたかった」とし、以前から綿引さんの個展に行って作品を見る機会が何度もあり、依頼することを決めたという。
8畳の和室の4枚のふすまに描かれた新たなふすま絵「桜花小禽図(おうかしょうきんず)」は、春の華やかさと夏の訪れを感じさせる情景を色鮮やかに描いている。「当初は春夏秋冬の四季を描く構想もあったが、大神宮といえば桜の印象が強いことから、春に焦点を当てることにした」と話す。「桜といえば海老川も名所なので、海老川やよく目にする身近な小鳥のスズメやカワセミ、ルリビタキ、メジロも描いた」とも。
ふすま絵の制作に当たり、綿引さんにとって初の試みとなる杉板への描画となった。下処理には2~3カ月を要し、絵の具は古くから使われている天然絵の具にこだわったという。さらに、平安時代の仏画模写や修復技法の知識を生かし、剥落を防ぐ処理も施した。構図は風が流れるようなイメージで、初夏の雰囲気を感じさせる朝顔も描いている。綿引さんは「子どもの七五三でも世話になった大神宮のふすま絵を手がけることができ、非常に光栄」と話す。
新社務所への移転は4月7日。ふすま絵が設置される場所は、10月20日の例祭における献幣使の控室のほか、職員の書道や雅楽の稽古場としても利用される予定。